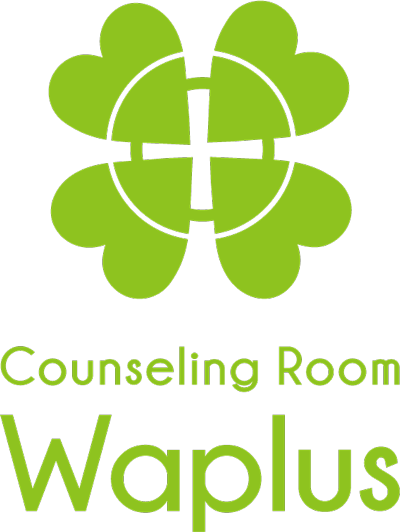相談室便り バックナンバー60
みんなが際立つ友人関係
~影があるから光がある~
華やかな人になりたい…
寒くなって日が沈む時間が早くなりましたね。暗い時間帯が増えてくると、気分も暗く沈みがちになることはありませんか。成績が下位に落ちたり、友だち作りがうまくいかなかったりして、自信をなくしたという相談を受けるときがあります。自信が持てないときほど人の陰に隠れたくなり、自分の中にある暗い影の部分を隠したくなるかもしれません。
ところが、一見華やかで自信を持っていそうな生徒からも「友達の前では明るくて陽キャに見られますけど、実は私、陰キャなんです。」というような話を聞くことが増えてきたように思います。友だちにはつまらない人だと思われたくないから、明るい自分を演じていると言います。
ただ、そうやって人前で明るく振舞おうとするほど、気疲れして、かえって暗い気持ちになってしまうことがあります。
影の行動化
多かれ少なかれ暗くネガティブな部分は誰にでもあるものですが、それを否定すればするほど自分らしさを見失ったり、ストレスがたまってきたりすることがあります。
スイスの心理学者C・ユングは、認めたくない自分自身の人格の側面を「影(シャドウ)」と呼びました。たとえ意識してポジティブな自分を演じていても、無意識のネガティブな自分を否定していれば、だんだんその暗い影が濃くなってきて、やがて表面化・行動化すると言うのです。
たとえば、ずっといい子を演じてきた人が突然悪さをしてしまったり、言いたいことを我慢し続けた人がストレス性の病気を患ったりすることがあります。そのようなときは自分が生きてこなかった影の側面と向き合い、統合していくことが、自己実現につながるとユングは考えました。
陰影の美
そもそも日本人は不安遺伝子を持っている人の割合が高いという説があります。リスクを負わず、シャイでネガティブ思考の人は比較的多いのかもしれません。文学の世界においても、海外の作品と比べて暗い印象があるのではないでしょうか。
作家の谷崎潤一郎は「陰翳礼賛(いんえいらいさん)」という随筆の中で、明治以降の日本は近代化が進み、電灯の明かりが部屋の隅々まで照らすようになって、陰影の美がなくなったとなげいています。西洋人は真っ白な壁紙を好むのに対し、日本人は砂壁のような薄暗い空間を好みました。白いご飯も暗い所で黒い器に盛られているほうが美しくて、食欲を刺激します。
夜の暗い部屋の中で襖から漏れてくる月灯りに美しさを感じるように、陰の多い環境であるがゆえに、日本人は自然と陰影の中に美を見出してきたと言います。一見暗く物静かに見える人でも、モノづくりや趣味の世界では心を躍らせているから、日本人の持つ芸術や文学、職人、オタク文化が発展したのかもしれません。
陰と陽の両面を見る
東洋思想では月と太陽、女と男、裏と表など、陰と陽が補い合うことで宇宙が成り立っているという考え方があります(陰陽五行説)。人のある側面だけ見て「陰キャだ」「陽キャだ」と決めつけるのではなく、陰と陽の両面を見ることで、そのコントラストから新たな魅力を発見することができます。明るい陽の部分だけ見ようとしても、陰と陽のバランスが崩れれば、その人らしさが見失われてしまうのです。
一見物静かな子が時折見せる笑顔、一見にぎやかな子が時折流す涙が心に残るように、闇夜を照らす月明り、太陽を際立たせる影など両面を大切にすることで、美しい風景が描写されます。クラスの風景や友人関係においても、陰の努力や黒子の役割など、自分や友人の中にある陰影を礼賛できたら、みんながより魅力的に映るのかもしれません。