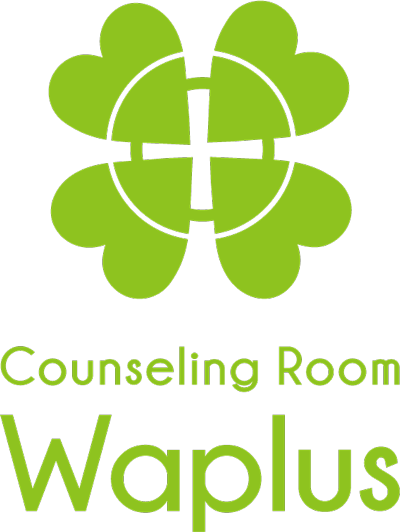相談室便り バックナンバー61
食が変われば心が変わる
~栄養療法のススメ~
気疲れの原因最近、疲れやすいと感じることはありませんか?気力がなくなったり、気分が不安定になったりする要因として、日々のストレスだけではなく、食べ物による影響も指摘されています。
常に緊張した生活をしていると、副腎という臓器から緊張ホルモンが分泌されます。身体が休んでいても頭では悩んでいたり、気を張った生活をしたりしていると、緊張ホルモンが出っぱなしになり、落ち込みや不安、イライラなどの症状が出やすくなることがあります(副腎疲労症候群)。
その緊張を緩和するには、上手に切り替えてリラックスする時間を設けること、質の良い睡眠を取ること、そして、内臓に負担のかからない食事をすることです。いくらワクチンで予防しても、薬で治しても、偏った食生活を続けていれば、心身の免疫力は弱ったままになり、不調につながりやすくなります。
腸内環境で心を整える
腸は第二の脳(セカンドブレイン)と言われるほど、脳と密接な関係がある(脳腸相関)ことは知られるようになりました。幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンの多くが腸で作られるという説があるように、腸に負担がかかれば、当然メンタルにも影響が出てきます。
たとえば小麦に含まれているグルテンや乳製品に含まれるカゼインが腸に炎症を起こすという説があります。その火消し作業をするのが副腎から出る緊張ホルモンになりますが、ずっとその作業に追われることで、副腎に負担がかかれば、心も疲れやすくなってしまうのです。また、砂糖は腸内の悪玉菌が好きなエサになります。
狩猟採集時代の日本人は栗や貝、海藻を拾って食べ、農耕が始まってからはお米を中心にした食生活でした。しかし、戦後、甘い食べ物や小麦、乳製品、植物性油を使った食品、添加物の普及は、腸内環境の悪化と無関係ではないようです。
血糖値で心を安定させる
気分の不安定さを血糖値の観点から見ることもできます。砂糖や小麦は血糖値を急激に上げ、すい臓からインシュリンが出ることで血糖値を下げますが、また上げるときに緊張ホルモン(コルチゾール)を分泌させます。そのアップダウンを繰り返していれば、副腎が疲弊し(血糖スパイク)、血糖値が上がりにくくなれば、低血糖症による抑うつ、イライラ、だるさなどの症状が出やすくなります。
エナジードリンクやコーヒーなどのカフェインも緊張ホルモン(アドレナリン)や血糖スパイクに影響を与えるので、控えるとよいです。血糖値を安定させるには、血糖値が急激に上がらない食品を取ることと、よく噛んで食べること。
現代はあらゆる食品に砂糖や人口甘味料、ぶどう糖果糖液糖などが含まれるようになり、品種改良で果物の糖度も高くなっています。人類の歴史において、こんなにも糖度の高い食生活は経験していないのかもしれません。
身体から心を癒す
戦後、うつ病やアレルギー、婦人科系の病気などが増えてきたのは、戦前は今ほど取っていなかった砂糖、小麦、乳製品、植物性油などとの関連を指摘する専門家もいます。また、これらの食品は依存性があるので、やめられない止まらない状態になりがちです。
栄養療法による効果は遺伝的要因や食文化、ストレス環境など個人差が大きいので、量と質、期間は試してみないとわかりません。ただ、実践できた人からは身体が軽くなった。気持ちが落ち着いたという声を聞きます。メンタル症状の何割かでも食生活で改善できる可能性があるのです。
人は食べたものでできています。海藻類や根菜類、キノコ類、魚介類、お米を中心に日本人に合った食生活、自分に合った食生活を見つけられると気力アップにつながります。ご興味のある方は、腸内環境を整えることで心を整え、血糖値を安定させることで心を安定させる栄養療法を試してみてください。